前回の記事では、JPYCを「日本円のデジタルマネー版」として紹介した。
では実際に、銀行にお金を預けるのと、JPYCを利用するのでは安全性にどのような違いがあるのだろうか。
本稿では両者の制度設計を整理し、その特徴を比較していく。
⭕️銀行預金の安全性
まずは銀行預金の仕組みを確認してみよう。
銀行の最大の役割は「預金を集めて融資を行う」ことである。
銀行にとって預金は、単なるお金の保管場所ではなく、企業や個人に貸し出すための原資だ。
したがって、私たちが銀行に預けたお金は、表面的には「口座に残高がある」と表示されているが、実際には銀行がその一部を貸し出し、運用しているというのが実態である。
この構造にはメリットもある。銀行が効率よく融資を行うことで経済が回り、企業は投資や事業拡大を進められる。個人も住宅ローンや教育ローンといった形で資金を利用できる。
一方で、リスクも存在する。万一銀行が過大な貸し出しや投資に失敗し、経営が行き詰まった場合、預金者のお金はどうなるのか、という問題が生じる。
日本ではこのリスクに対応するために「ペイオフ制度」が整備されている。
ペイオフ制度とは、銀行が破綻した際に、預金者1人あたり1000万円とその利息までを預金保険機構が保護する仕組みである。
ただし注意が必要なのは、1000万円を超える部分については、銀行が保有する資産の清算状況に左右される点だ。場合によっては一部しか戻らない可能性もある。
例えば、1つの銀行に3000万円を預けていた場合、制度上確実に守られるのは1000万円と利息のみで、残りの2000万円は最悪の場合失われることになる。
つまり銀行預金の安全性は、「国家による預金保険制度」と「銀行そのものの経営の健全性」、この二つに依存しているといえる。
⭕️JPYCの安全性
JPYCは「資金決済法」に基づいて発行される前払式支払手段である。
一般的な暗号資産のように価格が大きく変動するわけではなく、1円=1JPYCを基本とする円建てステーブルコイン的な存在として設計されている。
利用者がJPYCにチャージした資金は、その全額が発行元によって信託銀行などに預けられる。
この「資金の全額保全」が法律で義務付けられているため、仮に発行会社が破綻したとしても、信託銀行に預けられた資金が利用者に全額返還される仕組みになっている。
ここで注目すべきは、銀行預金のように「保護上限1000万円」といった制限がない点だ。
制度上、チャージした額はすべて守られることが前提になっている。
ただし、JPYCはあくまで「資産を増やす手段」ではなく、「決済や送金に使うためのお金」という位置付けである。銀行預金のように利息がつかない点は留意すべきだろう。
⭕️両者の比較
ここで銀行預金とJPYCを整理して比較してみる。
| 項目 | 銀行預金 | JPYC |
|---|---|---|
| 保護制度 | ペイオフ(1000万円とその利息まで) | 信託保全により全額が返還対象 |
| 利息 | あり(低金利) | なし |
| 利用範囲 | 預金、振込、融資など幅広い金融機能 | デジタル決済・送金に特化 |
| 発行主体 | 銀行(金融機関) | 事業会社(JPYC社) |
この表から見えてくるのは、両者がそもそも目的も制度も異なる存在であるという点だ。
銀行預金は、経済全体を回すための「信用創造」の仕組みに組み込まれており、社会基盤の一部として設計されている。
一方のJPYCは、個人や企業が日常的に使いやすいデジタルマネーとして、効率的で安全な決済を可能にすることを狙いとしている。
⭕️暮らしでの使い分け
では実際の生活で、どのように銀行預金とJPYCを使い分ければよいのだろうか。
銀行口座は、給与振込、年金受給、公共料金や税金の引き落とし、各種ローンの返済など、生活の基盤として不可欠である。資産の保管や管理の中心に据えるのが自然だ。
一方のJPYCは、利息がつかない代わりに、送金や決済のスピード感に強みがある。
銀行振込の場合、たとえば異なる銀行間であれば時間帯によっては翌営業日まで反映が遅れることもあるし、手数料が数百円かかるケースも少なくない。
これに対してJPYCは、ブロックチェーンを用いた取引であるため、即時かつ低コストで送金や支払いができる。
特にメリットがあるのは以下のような場面である。
- 割り勘や立て替え精算をする際に、即時に相手へ送金したいとき
- ネットショッピングで少額の決済を効率よく行いたいとき
- 海外送金や暗号資産の取引と組み合わせて利用するとき
銀行が「生活の大黒柱」とすれば、JPYCは「日常生活の小回りを効かせる便利なツール」と表現できるだろう。
両者は競合関係ではなく、むしろ補完関係にあると考えるのが現実的である。
⭕️投資や資産保全の視点から
さらに一歩踏み込んで「資産形成・投資」の観点からも整理しておきたい。
銀行預金は利息がつくものの、超低金利時代の日本では実質的に増える効果はほぼない。だが、その代わりに安全性と利便性が高い。
JPYCは利息がつかないため、長期的に資産を増やす場所ではないが、他の金融商品や暗号資産との組み合わせによって「決済専用ウォレット」として活用できる。
例えば、株式や投資信託を運用している投資家が、利益確定した資金を一時的にJPYCに置くことで、暗号資産市場やDeFi(分散型金融)にスムーズにアクセスできる。
このように、JPYCは「資産を置く場所」ではなく「資産を動かすためのパイプ」として機能するのだ。
DeFi(分散型金融)とは?
DeFi(ディーファイ)とは、ブロックチェーン上に構築された金融サービスのことを指す。
銀行や証券会社といった仲介機関を通さずに、世界中のユーザーが直接お金を貸し借りしたり、利息を得たり、資産を運用できるのが特徴。
例えば、従来は銀行を通じてしかできなかった「預金」「融資」「資産運用」といった仕組みが、スマートコントラクト(自動で動作するプログラム)によって誰でも利用できる。
そのため、手数料の安さや24時間稼働といったメリットがある一方、仕組みが複雑でハッキングリスクも存在する点には注意が必要だ。
JPYCとDeFiの将来性
現時点ではJPYCは「決済・送金に強みを持つデジタルマネー」としての役割が中心だが、DeFiの発展次第では新たな可能性が広がるかもしれない。
例えば、ビットコインやイーサリアムを担保にしてJPYCを借り入れるといった仕組みは、すでに海外のステーブルコイン(USDCやDAIなど)で実用化されている。
日本円建てのステーブルコインであるJPYCにも、将来的に同様の仕組みが導入される可能性は十分に考えられる。
これが実現すれば、暗号資産を売却することなく円建て資金を確保できるようになり、投資家にとって大きな利便性をもたらすだろう。
ただし、制度面や規制の整備が必要となるため、すぐに実現するわけではない点には留意が必要だ。
⭕️まとめ
本稿では銀行預金とJPYCを比較し、それぞれの安全性を整理した。
- 銀行預金:ペイオフ制度により1000万円とその利息まで保護。社会的信用と金融機能の幅広さが強み。
- JPYC:資金決済法に基づき信託保全が義務付けられ、チャージ額は全額返還される仕組み。円建てステーブルコイン的な安定性を持ち、決済や送金のスピード感に強み。
結論として、両者は「どちらが優れているか」という二者択一の関係ではなく、制度設計が異なる二つの仕組みである。
銀行は資産を守る「土台」、JPYCは日常を支える「潤滑油」。両方を賢く使い分けることが、これからの資産管理の新しい常識になっていくだろう。
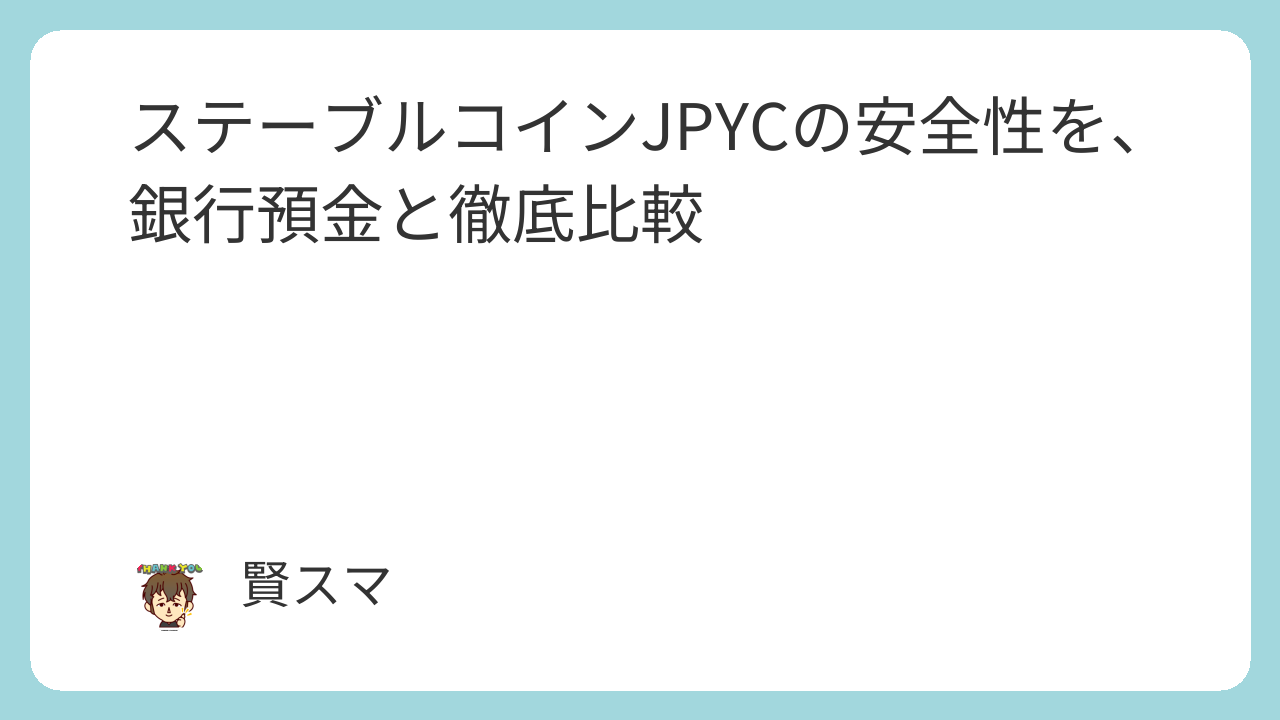
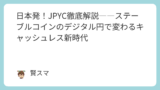
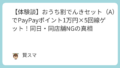
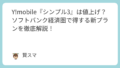
コメント